筆者のCCNA合格データまとめ【独学・勉強時間・スコア】
まずは私自身のCCNA合格時のデータをまとめます。
- 学習期間:約4か月
- 受験日:2025年9月13日
- 勉強時間:移動時間20分+夜10分~30分を継続、休日 1~4時間程度
- 初回Ping-t模試:45%(102問中46問正解)
- 最終Ping-t模試:78%(102問中80問正解)
- 使用教材:Udemy(インプット用)、Ping-t(演習・模試)、Packet Tracer(苦手分野の補強用)
- 受験回数:1回
数字だけを見ると「毎日かなり勉強していたのでは?」と思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。正直ベースに話すと1日あたりの勉強時間にはムラがありました。
平日は仕事で疲れて勉強しない日も多く、学習できたとしてもジムなどで体を動かしてリフレッシュした後に30分程度取り組むくらいでした。
休日も「4時間勉強」が最大で、それ以上の長時間学習は集中力が続かず、自分には難しかったです。
一方で、実務でほぼ毎日ネットワークスイッチに触れていました。日常的に設定変更などを行っていたため、インターフェースや基本コマンドの操作に抵抗がなく、この点は独学において大きなアドバンテージになったと感じています。
まとめると、私の勉強スタイルは「毎日長時間」ではなく、短時間でも継続し、実務経験を学習に結び付ける方法でした。
ただし、その経験があったとしても「一気に勉強するより、毎日少しでも継続して学ぶこと」が最も重要でした。
移動中の20分や就寝前の30分といった短い時間でも積み重ねることで、4か月間で合格レベルに到達できたのです。
CCNA合格に必要な勉強時間の目安【初心者・経験者別】
CCNAに必要な勉強時間は、受験者のバックグラウンドによって大きく変わります。
一般的には以下のように言われています。
ただし、これはあくまでも目安と捉えた方がいいかと思っています。実際には学習の仕方や集中力、理解度によって大きく変動します。
筆者の体験から見た勉強時間
私自身はネットワークスイッチを触る実務経験があったため、インターフェースの操作や基本的なコマンドには抵抗がありませんでした。この点は独学において有利に働いたと思います。
一方で、学習時間を正確に記録していたわけではありません。
私の場合、「平日30分・休日4時間」を4か月(約16週間)継続したとすると、合計は おおよそ150〜200時間程度 になります。
この結果から一般的に言われている勉強時間程度は勉強していたことにはなります。
時間よりも重視すべきポイント
振り返ると、勉強時間を細かく積算することよりも、模擬試験で安定して点が取れるかどうか を指標にする方が現実的だと感じました。
特にPing-tの模試は本番に近い形式で、自分の実力を測るのに役立ちます。
私自身は、Udemyで学習を進めている段階で先に受験日を決めてしまいました。
締め切りがあることで勉強にメリハリが生まれ、学習を継続する大きな原動力になったと思います。
CCNA独学におすすめの教材一覧
CCNAを独学で進める際には、教材の選定が合否を大きく左右します。私自身が利用した教材と、それぞれの活用方法・メリット・デメリットを紹介します。
Udemy【おすすめ度:★★★★★】
私が使った講座は以下の2つです。
これらの講座は、CCNA試験範囲を網羅的に学べる点が大きな魅力です。動画形式なので理解がしやすく、基礎固めに最適でした。
特に通勤中や移動時間中は、udemyを視聴する絶好の機会になりますので、倍速視聴で観ることを個人的にお勧めします!
とにかく動画を一通り観終えることに焦点を当てて取り組むことをお勧めします。
私が実際に勉強をして感じたことは、問題を解く中で知識が定着していくことです。
そのため、udemyで100%知識をインプットするのではなく、気持ち30%位を目標にしてあとはping-tでしごかれながら覚えていくルートが効率的かなと思います。
私がudemyを視聴した時間は以下の通りになります。
| 期間 | 合計時間(分) | 合計時間(時間) |
|---|---|---|
| 2025年5月18日〜6月13日 | 1225分 | 約20.4時間 |
| 2025年6月13日〜7月13日 | 1621分 | 約27.0時間 |
| 2025年7月13日〜8月13日 | 1029分 | 約17.1時間 |
| 2025年8月13日〜9月13日 | 501分 | 約8.3時間 |
白本【おすすめ度:★★★☆☆】
有名な「白本」も活用しましたが、私は 補助教材 として位置づけていました。
Udemyやping-tで理解が不十分な箇所に直面したときに参照する形です。
白本でもよくわからかった場合は、ChatGPTを頻繁に活用しました。
「初心者でもわかるように説明して」といった形で質問し、一から理解を深めるのに役立てました。
ping-t【おすすめ度:★★★★★】
Udemyと並行して、ping-tを使って問題演習を進めました。
学習スタイルは大きく2つです。
最初~中盤までは4択問題を中心に行い、直前期にはコマンド問題も絡めながら練習しました。
「お気に入り機能」を活用すると、
間違えた問題や不安な問題に絞って復習が行えるため、効率が上がります。
Packet Tracer【おすすめ度:★★★☆☆】
知識を定着させるには、実際に手を動かしてコマンドを入力することが効果的です。
Packet Tracerはその点で非常に役立ちました。
特に苦手な分野においてpacket tracerは効果的だと感じています。
私は特にACLやポートセキュリティなどでつまずいた際にPacket Tracerを利用し、実際にコマンドを打ちながら理解を深めました。
ChatGPT【おすすめ度:★★★★★】
CCNAの学習を進める中で、私は ChatGPTを積極的に活用 しました。
不明な点があれば雑に質問しても答えてくれるため、「嫌な顔をせずにいつでも解説してくれる先生」が一人いるような感覚です。
令和の時代にAIを使わない学習は正直もったいないので、積極的に活用していきましょう。
模擬問題を活用し得点率と苦手分野を確認
CCNAの試験対策において、ping-tの模擬問題は「実力を測るだけでなく、弱点を可視化するツール」として非常に有効です。私は主にping-tの模試を活用し、次のような学習サイクルを徹底しました。
- 模擬問題を一度解いた後、
間違えた問題や正解したけれど不安に感じた問題をすべて「お気に入り機能」でマーキング - そのリストを中心に復習を繰り返すことで、効率よく弱点を潰す
- 間違えた分野は演習問題で復習し、理解がそもそも曖昧な場合はUdemyに戻って基礎を確認
このように
模試 → 復習 → 苦手分野の演習 → 必要ならUdemyに戻る
というループを繰り返すことで、少しずつ正答率を上げることができました。
私は5月から9月にかけて計8回の模試を受験しました。
| 受験回数 | 受験日 | 正解数 | 出題数 | 正答率 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 2025/5/11 | 46 | 102 | 45% |
| 2回目 | 2025/8/8 | 74 | 102 | 72% |
| 3回目 | 2025/8/14 | 75 | 102 | 73% |
| 4回目 | 2025/8/24 | 76 | 102 | 74% |
| 5回目 | 2025/8/25 | 82 | 102 | 80% |
| 6回目 | 2025/8/29 | 83 | 102 | 81% |
| 7回目 | 2025/9/7 | 84 | 102 | 82% |
| 8回目 | 2025/9/12 | 80 | 102 | 78% |
初回は正答率45%と低いスタートでしたが、復習を重ねるごとに着実にスコアは上昇しました。直前期には80%を超える回もあり、合格への自信につながりました。
模擬問題に取り組んでいると、どうしても途中で心が折れそうになることがあります。
しかし、繰り返し模試に挑戦し、復習を重ねることが得点力アップの最短ルートだと考えています。
また、模試を解くことで自分の苦手分野が浮き彫りになるため、効率よく重点的な学習が可能になります。
(※苦手分野になるため、精神的な負荷は高いですw)
まとめ:CCNA独学でも合格できる勉強法のポイント
ここまで、私がCCNAに合格するまでの学習データや、実際に活用した教材・模擬問題での取り組み方を紹介しました。
振り返ってみると、合格に近づくためのポイントは以下の通りです。
独学でも合格は十分可能
CCNAは出題範囲が広いため不安を感じる人も多いですが、正しい教材選びと学習サイクルを回せば独学でも十分合格可能です。
私自身も仕事やジムの合間に少しずつ積み重ね、4か月で合格することができました。
これからCCNAを目指す方は、勉強時間にこだわりすぎず、模試の点数を指標にするのもおすすめです。
模試での得点推移を基準にすれば、自分に必要な学習量が見えやすくなり、学習計画や目標も立てやすくなると思います。
CCNA学習を始めたものの、模試の点数が伸びずに不安を感じている方へ。
私自身も最初はPing-t模試で45%しか取れませんでしたが、復習と継続で80%まで引き上げて合格できました。
同じように点数が伸び悩んでいる方は、ぜひこちらの記事を参考にしてください。
勉強を積み重ねていよいよ受験!という方には、試験当日の流れを具体的にイメージしておくことが大切です。
試験前の持ち物チェック、直前の勉強方法、会場での注意点など、実際に受験した体験談をまとめました。
「当日の不安を減らしたい」という方におすすめの記事です。




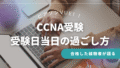
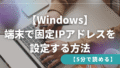
コメント