はじめに
社会人でCCNAを勉強していると、「仕事が忙しくて勉強時間が取れない」「模試の点数が全然伸びない」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
私も最初にPing-tの模擬試験を受けたときは45%程度しか正解できませんでした。
(何なら集中力が持たなくて途中で寝ました笑)
それでも、通勤や夜のスキマ時間を活用して約4ヶ月間コツコツと勉強を続けた結果、最終的には80%以上を安定して取れるようになり、無事CCNAに合格できました。
この記事では、私がどのように学習を進めて合格できたのかを体験ベースで紹介します。
本文中では、実際にPing-tの模擬問題で記録した点数推移をグラフで公開しますので、「どれくらい点数が伸びるのか」を具体的にイメージしたい方の参考になれば幸いです。
筆者のCCNA合格時のデータまとめ
本題に入る前に筆者のCCNAの受験した時のデータをまとめました。
すべてを記録しているわけではありませんが、おおよそ下記の通りになります。
- 学習期間:約4か月
- 受験日:2025年9月13日
- 勉強時間:移動時間20分+夜10分~30分を継続、休日 1~4時間程度
- 初回Ping-t模試:45%(102問中46問正解)
- 最終Ping-t模試:78%(102問中80問正解)
- 使用教材:Udemy(インプット用)、Ping-t(演習・模試)、Packet Tracer(苦手分野の補強用)
- 受験回数:1回
※最後のping-t模試で7割なのはいったんスルーしていただけると嬉しいです。笑
受験までに準備した期間は約4か月になり、働きながら勉強を進めました。
使用した教材と学習環境
私がCCNAの学習にあたって使用した教材は以下の3つです。
Udemy、Ping-tの学習記録はのちほどグラフでご紹介します!
学習の進め方(時系列)
詳しい勉強方法はこちらの記事で解説しています。
インプット期(1~2か月目)
最初の2か月は、とにかく Udemyでの動画視聴 をメインに進めました。
通勤時間やそのほかの移動時間(平均すると20分前後くらい?)やお昼休憩中を活用し、コツコツ視聴を重ねました。
帰宅後は、その時のモチベーションにもよるのですが、ある時は追加で視聴するような感じでした。
この時は可能な限り、勉強しない日は作らないことを意識していました。
たとえ勉強時間が5分でもやればOKくらいの間隔です。
この学習スタイルを最初に作ることでいきなり長時間勉強を行い、モチベが下がって勉強しなくなる状況を防ぐことができたと考えています。
ちなみにUdemyの視聴時間は、特に6月に学習時間がピークに達しており、この時期に最も多くのインプットを行っていたことがわかります。
| 期間 | 合計時間(分) | 合計時間(時間) |
|---|---|---|
| 2025年5月18日〜6月13日 | 1225分 | 約20.4時間 |
| 2025年6月13日〜7月13日 | 1621分 | 約27.0時間 |
| 2025年7月13日〜8月13日 | 1029分 | 約17.1時間 |
| 2025年8月13日〜9月13日 | 501分 | 約8.3時間 |
演習期(3か月目)
Ping-tは最初の1,2か月でもちょこちょこ解いていたのですが、インプットの終わりが見えたころから徐々に、Udemyの視聴からPing-tの演習問題中心に学習を切り替えていきました。
ここら辺から10日に1回くらいの間隔でPing-tの模擬問題は解いていき、理解の進捗度合いは測るようにしてました。
当時は1週間くらい経ったからやろーくらいの認識でしたが、意外と等間隔で受けていて自分偉いと思いました笑
仕上げ期(4ヶ月目・直前期)
試験直前の1か月は、弱点分野の克服に集中しました。
特にIPv6やポートセキュリティなど、理解が曖昧な分野については Packet Tracer を使ってコマンドを実際に入力し、動作を確認することで知識を定着させました。
また、この時期はPing-t模試も引き続き行いました。詳しいことは事象で話しますが、最終的には78%〜82%を維持できるようし、試験に臨める状態に仕上げました。
コマンド問題については、いまいちどのような感じで出題させるか分からず、ping-tの最近公開された新しいコマンドツール問題で対策しました。
模試の成績推移
CCNAの学習において、私が一番参考にしたのが Ping-tの模擬試験 です。
最初に受けたときの正答率は45%(102問中46問正解)。「厳しいな」とは感じましたが、同時に「初めてだし、こんなものか」と思ったのも正直なところです。
ちなみに、最初の頃は模擬試験の最中に集中力が切れてしまい、30分ほど寝てしまったこともあります(笑)。
そこからは、アウトプット中心に切り替えたことに加え、模擬試験の復習を丁寧に行ったことが点数上昇に直結しました。
間違えた問題は解説を確認するだけでなく、苦手な分野は再度Udemyの該当講義を見直して補強しました。
この繰り返しによって、少しずつ点数が安定して伸びていきました。
結果の推移は以下の通りになります。
| 受験回数 | 受験日 | 正解数 | 出題数 | 正答率 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 2025/5/11 | 46 | 102 | 45% |
| 2回目 | 2025/8/8 | 74 | 102 | 72% |
| 3回目 | 2025/8/14 | 75 | 102 | 73% |
| 4回目 | 2025/8/24 | 76 | 102 | 74% |
| 5回目 | 2025/8/25 | 82 | 102 | 80% |
| 6回目 | 2025/8/29 | 83 | 102 | 81% |
| 7回目 | 2025/9/7 | 84 | 102 | 82% |
| 8回目 | 2025/9/12 | 80 | 102 | 78% |
※8回目は、操作ミスなのかサイトの表示が若干バグっていたのか模擬形式で解けなかったので、自由演習(100問 + 2問)で計算しています。

棒グラフで表すとこんな感じです。

2回目以降は、Udemyの視聴も一通り視聴し、ping-tでアウトプットを繰り返していたので急に成績が伸びた形となります。
3回目以降は、「模擬問題 + 復習 + 自由演習」のサイクルを回して少しずつ点数を伸ばしていった形になります。
本番試験の結果
試験当日は緊張しつつも、模試で繰り返し練習していたこともあって落ち着いて臨むことができました。
実際の結果は以下の通り、セクションごとに70〜100%の正答率となりました。
- Automation and Programmability:70%
- Network Access:90%
- IP Connectivity:80%
- IP Services:100%
- Security Fundamentals:80%
- Network Fundamentals:70%
総合するとおおよそ 81% のスコアで合格です。(単純な合計の平均値になりますが)
面白いことに、最終的な本番試験の結果は、Ping-tの模擬試験で取っていたスコアとほぼ同じ水準でした。
当たり前といえば当たり前ですが、積み上げた勉強の成果がそのまま当日に発揮された ということを強く実感しました。
正直なところ、各セクションが実際のどの問題に対応しているのかはよくわかりません。
それでも結果を見ると、「苦手分野をできる限り減らそう」と意識して取り組んできた学習の積み重ねが、点数に表れていると感じました。
また、IP Servicesが100%だったのは意外で、特別に得意だと意識していたわけではなく、結果を見て「あ、満点だったんだ」と思った程度です。
一方で、Network FundamentalsやAutomationは70%に留まりましたが、どの問題がこのセクションに該当しているのか明確にはわからず、今後この分野を勉強し直すモチベーションは正直あまり高くありません。笑
合格して感じたこと
CCNAの勉強を始めた当初は、模擬試験で45%しか取れず、到底合格に届く点数ではありませんでした。
それでも、毎日の通勤や夜のスキマ時間を使って少しずつ学習を積み重ねた結果、最終的には本番で81%を取って合格できました。
今回の経験を通じて感じたのは、完璧に仕上げる必要はなくても、地道な勉強の積み重ねで合格点には到達できる ということです。
社会人の場合、毎日同じだけの時間を取るのは難しく、学習の波もあると思います。
私自身、集中力が続かず模試中に寝てしまったこともありましたし、学習意欲が高い日もあればほとんど進まない日もありました。
それでも、教材を組み合わせて「インプット → アウトプット → 弱点補強」の流れを回したことで、着実に点数を伸ばすことができました。
これからCCNAを目指す方へ伝えたいこと
とにかく少しでもいいから毎日学習すること UdemyとPing-tは神教材(この2つがあれば十分戦える) 苦手な分野を作らないこと(理解が浅いところは早めに潰しておく)
正直、今は合格できたことで一区切りがつき、さらに勉強を続ける強いモチベーションはありません。
ですが、今回の合格体験を通じて「やればできる」という自信がついたのは大きな収穫です。
まとめ
今回は、社会人として働きながら約4か月の学習でCCNAに合格した体験を紹介しました。
ポイントを整理すると次の通りです。
- 学習期間:約4か月
- 学習方法:Udemyで基礎をインプット → Ping-tで演習・模試 → Packet Tracerで苦手分野を補強
- 成績推移:Ping-t模試は45%からスタートし、最終的には78〜82%まで上昇
- 本番試験:総合約81%で合格
私自身は、UdemyとPing-tを中心に学習を進めたことで合格につながった と感じています。
もちろん人によって合う教材は違いますが、同じように独学でCCNAを目指す方には参考になるはずです。
これからCCNAを目指す方へ
最初の模試で点数が低くても気にしない 少しずつでも毎日勉強する 私の場合は UdemyとPing-tを中心に進めた(参考までに) 苦手分野を作らない
今回の記事では「勉強法と成績推移」を中心に紹介しました。
試験当日の流れや会場の雰囲気、さらに詳しい学習方法については別記事でまとめていますので、あわせてご覧ください。






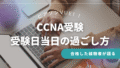
コメント